
シンポジウム「先端技術と人間のいのち:芸術における人生の形態と認識の課題に向けて」は、演劇で用いられる先端技術が、人間の姿かたちや認識に対する従来の考え方にどのように影響するかを考察するものです。
現代演劇では、人工知能、モーションキャプチャ、バーチャルリアリティ、ホログラフィック投影といった先端技術がますます多用されるようになり、それに伴っていくつかの問題が提起されています。アーティストがロボットやデジタルアバター、あるいは人工知能によって生み出されたキャラクターと同じ舞台に立つ際、人間の存在はどう扱われるのか?観客は、公演中に非人間的な存在生身の人間以外の存在をどのように捉えるのでしょう?実世界と仮想世界の両方にパフォーマンスが同時に存在するとき、その「人間のいのち」とは何を指すでしょうか?アンドロイドが、かつては人間だけのものと考えられていた行動を示すようになったとき、私たちは自らをどう認識し、また表現すべきでしょうか?
本シンポジウムでは研究者、演出家といった先端技術と演劇に携わるゲストが集まり、これらの問題について議論を行います。
【日 時】2025年10月21日(火)14:30~18:00 (14:00開場)
【会 場】大阪大学中之島芸術センタースタジオ(大阪大学中之島センター3階)
【入場料】無料・先着60名程度 ※事前申込み不要です。直接会場にお越しください。
プログラム:
第1セッション 14:30~16:00
使用言語:日本語|Language: Japanese
登壇者:平田オリザ・奥秀太郎
第2セッション 16:30~18:00
使用言語:英語|Language: English
登壇者:山本裕紹・ダニエル・フルベック(Daniel Hrbek)・ ステファン・ケーギ(Stefan Kaegi)
※ダニエル・フルベック(Daniel Hrbek)・ ステファン・ケーギ(Stefan Kaegi)の両名はオンラインでの参加です
司会|Moderator:カスティリャンチャンカ・イリーナ(Kastylianchanka Iryna)
【登壇者来歴】
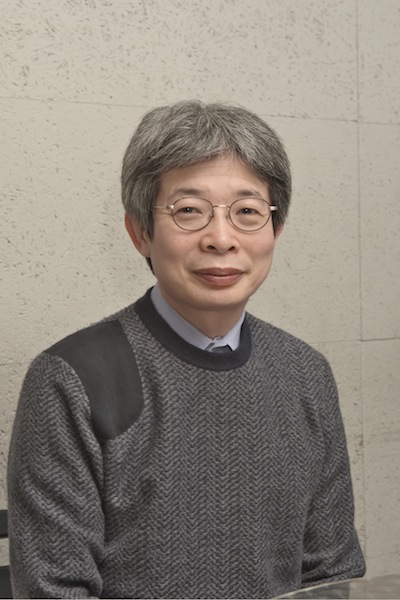
◇平田 オリザ(劇作家・演出家・青年団主宰・芸術文化観光専門職大学学長・青森県立美術館館長)
1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞、2002年『上野動物園再々々襲撃』で第9回読売演劇大賞優秀作品賞、2019年『日本文学盛衰史』で第22回鶴屋南北戯曲賞を受賞。2011年フランス文化通信省より芸術文化勲章シュヴァリエ受勲。2006〜2013年まで、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(現 COデザインセンター)で教鞭をとり、石黒浩研究室と協働してロボット・アンドロイド演劇作品を発表、国内外でも公演を行う。2019年より兵庫県豊岡市に移住し江原河畔劇場を設立。豊岡演劇祭フェスティバル・ディレクターもつとめる。2021年にパフォーミングアーツと観光を学べる日本初の公立大学「芸術文化観光専門職大学」開学、初代学長に就任。

◇奥 秀太郎(映画監督・映像作家)
劇場公開作品として「壊音」「日雇い刑事」「日本の裸族」「赤線」「カインの末裔」(ベルリン国際映画祭正式出品)「USB」他15作を監督。舞台演出作品として「黒猫」「ペルソナ」AKB版「仁義なき戦い」等、NODA・MAP、東宝、宝塚歌劇団、大人計画から、能、歌舞伎、落語と多岐に及ぶ。 最近ではVR、3D映像など最新技術を駆使した能舞台の演出で日本および世界各地で話題を呼んでいる。最新作は『VR能攻殻機動隊』。2022年、東京大学 先端科学技術研究センターJST ERATO 稲見自在化身体プロジェクト 「自在化コレクション」総合ディレクターに就任。

◇山本 裕紹 (教授・博士(情報理工学))
1994年東京大学工学部卒。1996年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。1996年徳島大学助手。2009年徳島大学講師。この間,東京大学大学院情報理工学研究科より学位授与。 2014年宇都宮大学准教授。2019年宇都宮大学教授。現在に至る。日本光学会理事(機関誌「光学」編集委員長)、IEC/TC110日本委員会委員長など光学・ディスプレイ関係の学協会委員・委員長を歴任する。

◇ Daniel Hrbek/ダニエル・フルベック
1999年よりシュヴァンダ劇場の常務取締役を務め、プラハ舞台芸術大学(DAMU)では演技と演出の教育者でもある。シュヴァンダ劇場ではこれまでに18作品の演出を手がけている。1994年には高い評価を得た劇団「CD 94」を設立し、芸術監督として8年間運営しながら欧州各国で公演を行った。演出家およびシュヴァンダ劇場の常務取締役となる以前には、チェコの著名な劇場で長年俳優として活動していた。

◇Stefan Kaegi/ステファン・ケーギ
動物や観客さえもが中心的な役割を果たす多様な形態で、ドキュメンタリー演劇、ラジオドラマ、遊牧的なコンセプト、都市空間におけるプロジェクトを創作する。ヘルガルト・ハウグ、ダニエル・ヴェッツェルと共にリミニ・プロトコル名義で劇団を主宰し、2011年のヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門銀獅子賞をはじめ数々の賞を受賞している。近年では、ポスト民主主義の現象を題材にした四部作『State 1-4』、ハンブルク・シャウシュピールハウスでの世界気候会議のシミュレーション、クラゲのインスタレーション『win<>win』、マンチェスター・フェスティバルでの都市散歩『Utopolis』などを上演している。

◇Iryna Kastylianchanka /カスティリャンチャンカ・イリーナ(大阪大学中之島芸術センター特任研究員・博士(演劇学))
ベラルーシ国立科学アカデミーにて美術史(演劇学)の博士号を取得。学術研究は現代演劇、古典文学の舞台化、演劇のグローバル化と異文化間交流の問題を専門とする。2009年から2016年までベラルーシ国立芸術アカデミー芸術史・理論学科にて講師、その後上級講師を務めた。現在の研究プロジェクト「演劇における革新的技術」では、革新的な技術(AI、VR、AR)を用いて構築された劇場空間において、人間と物体の相互作用を鮮やかに表現する欧州および日本の演劇作品に焦点を当てている。2023年より大阪大学中之島芸術センター特任研究員。